足の裏★素足裏
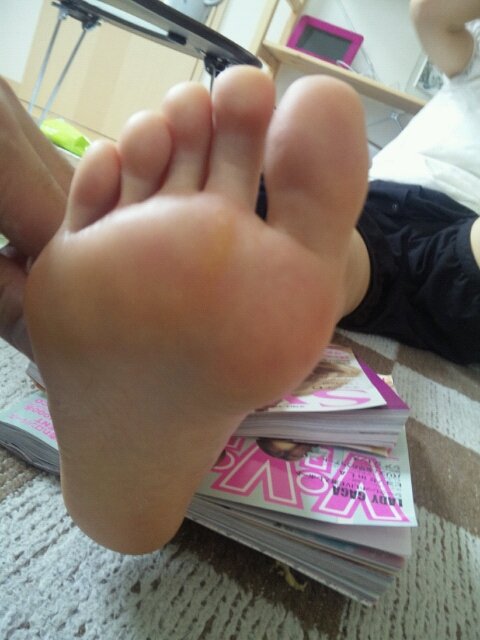 |
当BBSは女の子の素足が大好きな管理人が運営している、ガチの足フェチサイトです。
新しい掲示板を作りました。 ■足と脚の違い■ 足(foot)はくるぶし以下を、脚(leg)は太もも以下を指します。(参考画像) 当サイトは足フェチさん向けでございます →つま先、足裏の写っている画像 →足首以下が写ってない画像(脚フェチさん向け) →JC.JKの靴下 →アイドル/芸能有名人の足 |
2014/09/18 21:01
【足フェチ】掲示板利用ガイドライン【必読】 (4)2025/04/09 01:35
足の裏★素足裏 (1683)2025/03/31 11:09
女靴、靴下単体専用スレ (521)2025/03/19 00:17
JK/JCの素足 その2 (2261)2025/03/08 00:40
メアド/ID/画像交換スレ (1165)2024/12/09 14:06
生足画像総合 (899)2024/10/31 05:57
ロリっ子専門 (2694)2024/09/12 22:41
【足画】女神のおみ足専スレ【自撮り】 (495)2024/03/10 01:01
JC/JKの靴下 その2 (1499)2023/08/29 09:08
フットカバーはおいしそう (483)2022/07/13 08:39
臭そうなスニソ/くるぶし (2506)2022/06/22 23:17
足フェチ/M男動画サンプル (2347)2024/09/08 08:43
靴下・ソックス着用画像スレ (238)2021/11/29 08:33
素足にパンプス (653)2020/12/22 21:20
脚画像総合スレ (620)2020/11/30 23:48
【足画】オリ画像専スレ【貼り師】 (2480)2020/09/24 17:35
足コキ/足舐め/顔踏み/足責めスレ (400)2020/07/09 00:57
パンスト/タイツ (1079)2020/06/29 22:51
ほくろのある足裏限定のスレ (10)2020/01/11 14:30
【足フェチ】洋モノ総合【脚フェチ】 (60)2020/01/11 14:28
足フェチ動画倉庫(改) (165)2020/01/11 14:27
靴脱ぎ画像スレ (632)2020/01/10 18:20
素足にサンダル (1481)2020/01/04 12:38
【虹】二次足画像総合スレ (392)2020/01/04 12:32
ビーチサンダル(ビーサン)専スレ (348)2020/01/04 12:23
【わんこ】動物の画像【にゃんこ】 (50)2020/01/04 12:22
草履・下駄・浴衣・(和装)の素足 (141)2020/01/04 12:21
名前の分からないタレント足画像 (47)2020/01/04 12:19
使用済み靴下等を手に入れる話 (54)2020/01/04 12:17
フットネイルコレクション(芸能有名人) (156)2020/01/04 12:15
フットネイルコレクション(AKB関連) (111)2020/01/04 12:11
【徹底討論】足フェチとM男を一緒にするな!【足コキ】 (19)2020/01/04 12:06
フットネイルコレクション(梅野舞さま/高松リナさま) (18)2020/01/04 11:49
つま先アップ (660)2018/10/06 11:15
雑談/練習/足以外の画像 (226)2018/10/04 00:03
 まーくん様専用スレ
(83)
まーくん様専用スレ
(83) 2018/10/02 17:02
管理人より (85)2018/09/29 00:15
芸能・有名人の素足 (1029)2013/07/06 16:17
JC/JKの靴下[満] (2977)2013/05/10 01:00
JK/JCの素足[満] (3000)2013/08/02 19:09
 【閲覧注意】女子小◯生とセ☆クスする方法【画像】
(6)
【閲覧注意】女子小◯生とセ☆クスする方法【画像】
(6) 2020/01/11 14:27
足フェチのためのライブチャットの遊び方 (8)2020/01/13 21:07
【CM】宣伝スレッド【あぴ】 (11)
交響曲第4番変ロ長調 作品60は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの作曲した4作目の交響曲。
スケッチ帳の紛失のため正確な作曲時期は不明だが、1806年夏ごろから本格的な作曲が始められている。この年はラズモフスキー四重奏曲集、ピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲、オペラ《レオノーレ》第2稿などが作曲されたベートーヴェンの創作意欲が旺盛な時期であり、この作品も比較的短期間に仕上げられている。10月中には作品が完成し、献呈先のオッペルスドルフ伯爵(英語版)に総譜が渡されたと考えられている。
ベートーヴェンの交響曲の中では古典的な均整の際立つ作品で、ロベルト・シューマンは、「2人の北欧神話の巨人(第3番と第5番のこと)の間にはさまれたギリシアの乙女」と例えたと伝えられている。また、エクトル・ベルリオーズは「スコアの全体的な性格は生き生きとしていて、きびきびとして陽気で、この上ない優しさを持っている」と評した。しかし、そのようなイメージとは異なった力強い演奏がなされる例もあり、ロバート・シンプソンは「この作品の持つ気品は『乙女』のものでも『ギリシア』のものでもなく、巨人が素晴らしい身軽さと滑らかさで気楽な体操をこなしているときのものなのだ。ベートーヴェンの創造物には、鋼のような筋肉が隠されている」と述べている。